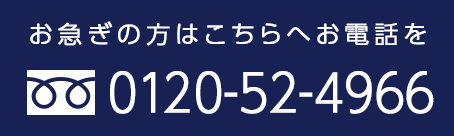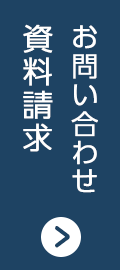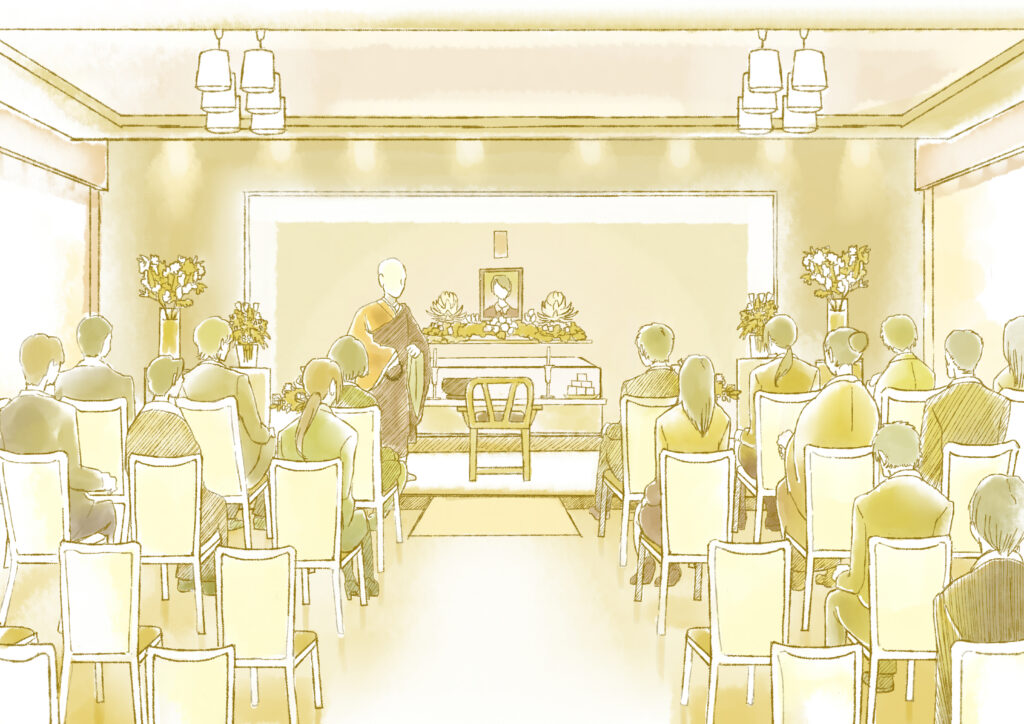こんにちは。
ありがとうで送るお葬式®
家族葬のウィズハウス新宮・ベルホール中本・ザ・スランバーズガーデン・そうそうの郷太地を運営しております中本葬祭の中本です。
昔から「どうしてお葬式には2日間という時間が掛かるものなのでしょうか?お通夜って必要なのですか?」という質問を頂くことがあります。
宗教的な理由はもとより、お通夜という時間はご家族にとっても非常に重要な時間と言えます。
本日は「なぜお通夜をする必要があるのか?」という事を中心にご紹介させて頂きます。
お通夜の意味
昔のお話からご紹介させて頂きますと、本来は亡くなった人が生き返る可能性があるので皆で夜通し見張っていましょうという考え方からという説や、夜を通して御遺体に魔物が入らないように見守っていたとか、猫股や火車といった魔物が御遺体を持っていかないようになどなど諸説あるようです。
いずれもちょっと科学で証明される時代ですので、このような言われが「迷信だから、だったらお通夜はなくても良いよね」という考え方を持つ方もいらっしゃるのだろうと思われます。
しかし、そのような昔からの言い伝えよりも、もっと現代的できちんとした意味がお通夜の日には存在します。
お通夜とは宗教、宗派の枠を超えてお斎(おとき)の目的である事が基本です。関西ではお通夜の後の食事をお斎(おとき)と言います。この言葉は斎場の「斎」と書きますが、これはお伽噺(おとぎばなし)の伽(とぎ)と同義語になります。つまり、皆で何かの話をするというのがお説(とき)のとき、お通夜の意味を指します。
お釈迦様がお亡くなりになった時にも「お釈迦様はああ言ってた、こんな話をされていた」と集まって話をしたという仏教の故事にも出てくるお話があります。
実際、告別式が終わった後にも皆で食事をして終了となるのですが、お帰りの電車や飛行機の時間も決まっていたりしますので皆でゆっくりあの人はああだった、こんな側面もあったという話をすることが実質、出来ません。様々な人からの話を通して、ご家族の知っている故人のイメージだけではなく、こんな男気のある人だったとか、こんな可愛い一面もあったなど色んな話をして頂く、皆と触れ合うといった事を通して、故人が確かに生きていたということを自身の中に取り込む作業と言えるかと思います。
例えばご弔問の方が多く、一人ひとりとそのような時間が取れなかったとしても、亡くなった故人の為に弔問いただいた方が泣いて下さってたり、「よく頑張ったね」といった労いの言葉を掛けている姿を見た時に「うちのお父さんは(お母さんは)立派な人だったんだな」と改めて理解する機会にもなります。
自身の大切な家族のためにお参りに来てくださったりですとか、涙を流してくださる姿を拝見して、有り難いなという感謝の気持ちが沸き起こります。
そうした事を通じて「この親の子供で本当に良かった」というお気持ちが芽生えてきます。これらは、理屈ではなく何より自分自身が体験したからこそ判るお話になります。
こうした事を通して、自身の中に故人の命を受け継ぐ(引き継ぐ)という意味が「伽・お斎・お説」お話をしてもらう事の本質ではないかと思います。
ですので、なるべく多くの人に来ていただきたいという形になり、昼も夜も行うことによりお参りをしていただきやすくしましょうというのが現在の形です。
やはり、昼は難しいけれど夜なら仕事も終わっているのでお参りに行けるという方も多く、そうして来てくださる皆さんの為に場を整えるのをご家族が故人に成り代わって行うというのがお通夜の意味となります。
もう一つの意味は、本葬である告別式の前の大事な準備としての意味合いもあります。近年はお通夜を行わず、1日で全てを終える「一日葬」といった形態もありますが、たった一日で全てを行うので、席順一つをとっても前日の通りとなるものも全て一からとなります、「あなたのお父さんってこんな人だったのよ」といったご親族の方から始めて聞くようなお話も、前日のお通夜があるので当日のお葬式を落ち着いて迎えられる訳ですが、そうした落ち着きもなく、故人へのお話の場もなくいきなり一日で迎えるというのはご家族にとっても様々なご負担を強いることになるものになります。
お通夜の意義とは
お通夜の意義とは、時間が緩やかな中で皆さんにご弔問に来ていただき、最期に記憶を集める作業をしているという側面もあるかと思います。
人は誰しも社会の一員として生きているわけですから、ご家族から見た姿が全てではなく、ご友人から見た姿、ご兄弟から見た姿、仕事場で見た姿・・・。そんな様々な社会で関係のある方が一同に同じ場所に集まって故人を悼むというのがお通夜やお葬式の本質的な意味ではないかと思います。
勿論、様々な状況や事情もあり、やむなく一日葬でという事を否定するつもりは全くありませんが、こうした背景や本質的な意味を理解した上でどのようなお見送りを選択されるかをお考えいただけたらと思います。
この記事の著者:(株)中本葬祭/専務取締役 中本 吉保